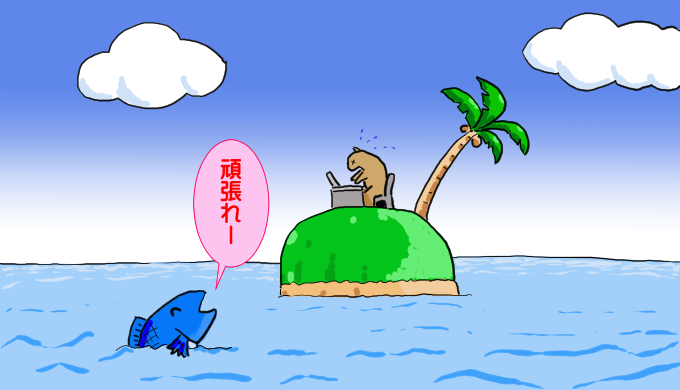入試レベルに達した受験生の勉強スケジュール
前回の”宅浪中盤のスケジュール(いつでも戻る覚悟が必要!?)“の続きである、宅浪終盤のスケジュールで、ある。
やはり、以前と同様、我が召し使いが、予備校や家庭教師で働いていた時の基準、特に家庭教師をしていた時の基準で、考察していく。
宅浪終盤のスケジュール
この段階で学ぶのは、過去問や模試過去問など、実際の出題形式のものを時間を決めて解いていく
発展レベル
の学習が主となる。
発展レベルの勉強の内容
この段階の勉強は、問題演習が主となる。
発展レベルの問題集に関しては、”宅浪の為の問題集(難易度が重要!?)”で扱っている。まあ、基礎レベルや応用レベルと違い、よく分からないって事は無いと思うが。
講義であれば、共通テスト対策講座や、大学別対策講座などの志望校別対策講座を受ける事となる。
応用レベルの勉強との違い
応用レベルの勉強と何が違うの?って聞かれたので、どこが違うのかを書いておくと、
応用レベルは、
実際に出題されるような問題を分野別に解き、
解法パターンなどを学ぶ
のが目的であるのに対し、
発展レベルは、
実際に出題される問題セットである過去問などを
受験時と同じ・もしくはちょっと短めの
時間を決めて解き、
大学との相性や、
時間配分の仕方や、
取らないといけない問題や、捨て問の
選別眼を養う
のを目的にしている。
大学との相性
これは結構重要で、自分に合うタイプの出題傾向なのか、合わないタイプの出題傾向なのかは、入試の結果にかなり影響してくる。
この出題傾向の問題は解きやすいな!って思える大学は、多少偏差値的に高くても、結構善戦して合格を勝ち取る事もあるし、逆に、解きづらいな、って思う大学は予想外に苦戦して、偏差値的には安全校でも足元を掬われる事も良くある。
いつどれくらいの年数分解くのか?
よって、実際に大学の過去問を解く事は色々な面で重要である。
これは、あくまで予備校にいた時の話であるが、まず大体7月~8月くらいに、受ける可能性のある大学の過去問を入試一回分解かせていた。
これで大学との相性を見て貰って、9月~10月ぐらいに三者面談で模試の結果等と総合的に考察し、志望校の絞り込みをしていた。
その後、一旦、応用レベルの勉強に戻り、11月前後から再び大学別講座や模試過去問、その後、また大学の過去問に挑戦させるってしていた。
この受験直前期の過去問演習は、受ける可能性のある大学の過去問を最低三年分は解こうね!って指導していた。
これは、スケジュールががっちり決まってしまっている予備校での例なので、スケジュールに柔軟性がある宅浪生であれば、
応用レベルの勉強がある程度進んだ段階で、
志望校の絞り込みを行う為に、
各大学入試一回分づつ、
応用レベルの勉強が終わったのち、
点数力を上げる為に、
各大学最低三年分
やるのが良いかな。
もちろん時間的余裕があれば10年分、20年分やってもいいし、やった方が良い。
受験終盤にかかる期間
これは、ある決まった”期間”ではなく、発展レベルの勉強に取り掛かってから、受験直前までとなる。
とはいえ、やっぱりそれ相応の期間は必要になる事が多く、普通、
三ヶ月から半年
ぐらいは、必要な人が多いかな。
応用レベルの時と同様、しっかり基礎レベルや応用レベルの内容が身についていれば、基礎レベルの学習時とは違い、極端に期間が長くなる事は少ない傾向にある。
前に戻る事を恐れない事も重要
ちゃんと応用レベルまで進めていれば、発展レベルに入ってから基礎レベルに立ち戻るって事は少ないかと思うが、
受験期間は一年
とか、期間を決めて宅浪しているような受験生は、基礎レベルがしっかりせずに発展レベルの学習をしてしまう事が多い。
自身のレベルにあった内容の学習レベルでないと、逆に勉強時間の無駄となり、より、浪人期間が長くなったり、下手をすると、受験自体を諦める事になりかねない。
大学にもよるが、もし、その大学の過去問の半分も出来ないようであれば、基礎レベルへいったん戻った方が良いか、と、犬は思う。

受験終盤のスケジュールは、その段階まで達すれば、三ヵ月~半年ぐらいかかるであろう

次の記事
【全受験生必須!】宅浪と模試(医学部受験で受けるべきおすすめ模試!?)
に続く・・・